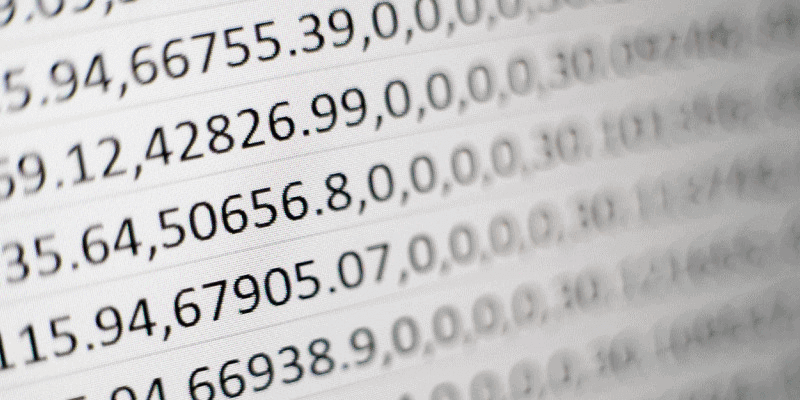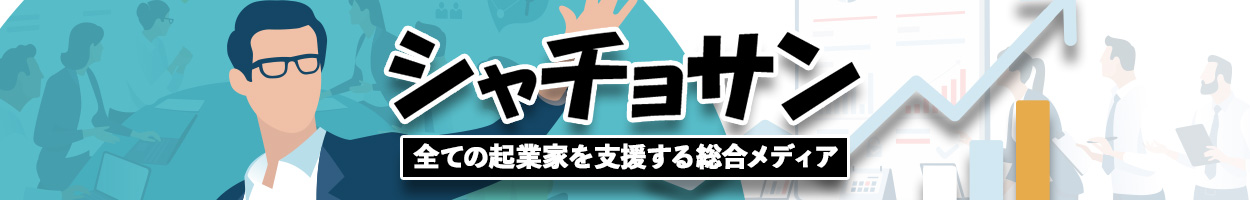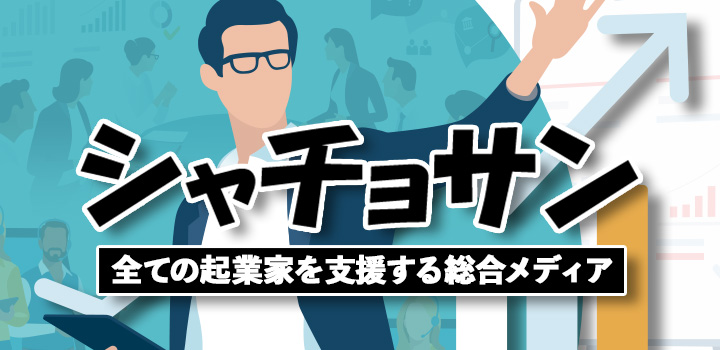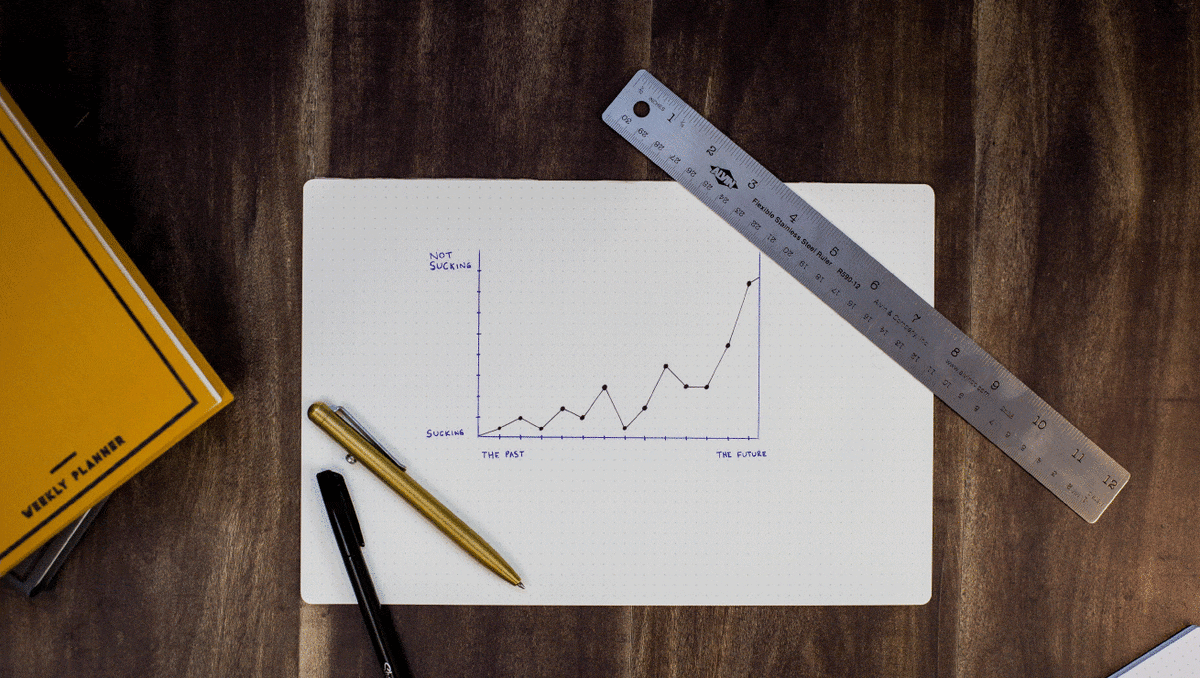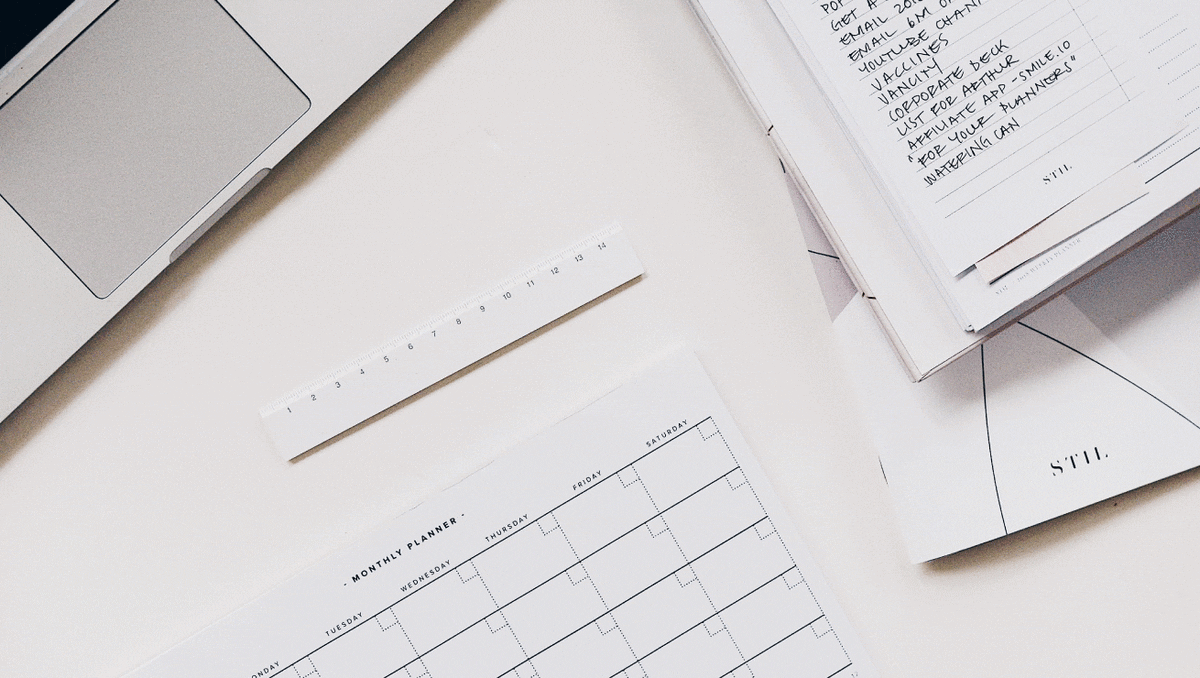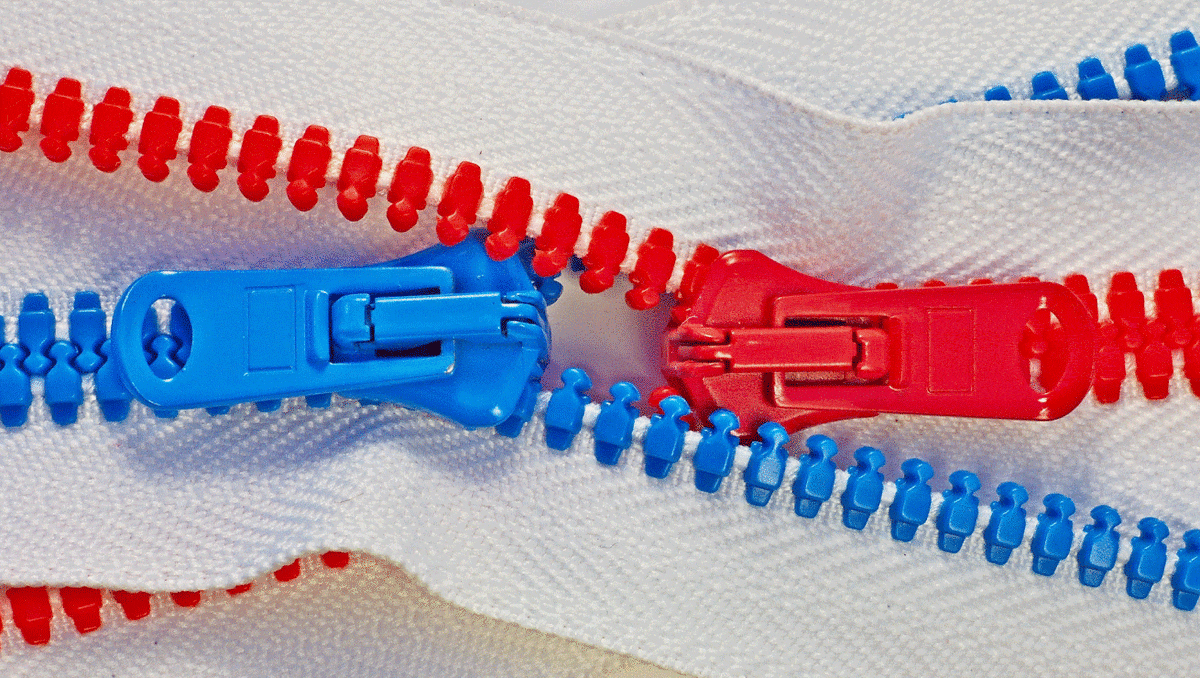ファクタリングによる会計処理は以下の3つのタイミングで必要となります。
- 売掛金が発生したタイミング
- ファクタリング契約をしたタイミング
- ファクタリング会社から入金されたタイミング
ファクタリング利用による手数料は
「売掛債権譲渡損」、未入金の場合は
「未収金」の勘定科目で仕訳します。
この記事では、ファクタリング利用による会計処理をタイミングごとに実例で紹介。
さらに、オフバランス化についても解説しています。
ファクタリングに関する会計処理の悩みが、きっと解消するはずです。
ファクタリングの勘定科目は「売掛債権譲渡損」で仕訳する
ファクタリングによって生じた手数料の勘定科目は、
「売掛債権売却損」で仕訳。
ファクタリング会社からまだ入金されていない場合の会計処理は、
「未収金」として仕訳します。
ファクタリングの利用によって会計処理が必要となるタイミングは以下の通りです。
- 売掛金が発生したタイミング
- ファクタリング契約をしたタイミング
- ファクタリング会社から入金されたタイミング
次の章で、それぞれのタイミングでの仕訳・勘定科目について解説します。
【実例】ファクタリングによる会計処理 仕訳・勘定科目を解説
この章では、ファクタリングによる会計処理を実例をもとに解説します。
前述した通り、会計処理は以下の3つのタイミングで実施。
- 売掛金が発生したタイミング
- ファクタリング契約をしたタイミング
- ファクタリング会社から入金されたタイミング
また、ファクタリング契約から即日入金されるケースもめずらしくありません。
即日入金のケースも含め、4つの仕訳・勘定科目を実例で見ていきましょう。
売掛金が発生したときの仕訳方法
1つ目の段階は売掛金発生時の仕訳方法です。
取引先へ商品やサービスを提供し、売掛金が発生した場合の仕訳方法となります。
| 借方の勘定科目 |
金額 |
貸方の勘定科目 |
金額 |
| 売掛金 |
1,000万円 |
売上 |
1,000万円 |
この際、売掛金となっている売上は
課税対象です。
ファクタリング契約したときの仕訳方法
2つ目の段階はファクタリングを契約した時の仕訳方法です。
ファクタリング契約時の仕訳方法は以下の通りになります。
| 借方の勘定科目 |
金額 |
貸方の勘定科目 |
金額 |
| 未収金 |
1,000万円 |
売掛金 |
1,000万円 |
ファクタリングの契約から、売掛債権売却額が入金までズレが生じる事があるでしょう。
3社間取引の際や即日入金できない状況の場合には「
未収金」で処理をします。
ファクタリング会社から入金されたときの仕訳方法
3つ目の段階は、ファクタリング会社から売掛債権の売却額が入金された時の仕訳方法です。
後述しますが、ファクタリング会社から受け取る譲渡代金は非課税になります。
| 借方の勘定科目 |
金額 |
貸方の勘定科目 |
金額 |
| 普通預金 |
900万円 |
未収金 |
1,000万円 |
| 売上債権売却損 |
100万円
(非課税) |
|
|
入金が完了した場合には、上記の通り仕訳をすることが可能です。
ファクタリング契約と入金が同日のときの仕訳方法
4つ目の段階は、ファクタリングと契約した段階で入金がされた場合の仕訳方法です。
| 借方の勘定科目 |
金額 |
貸方の勘定科目 |
金額 |
| 普通預金 |
900万円 |
未収金 |
1,000万円 |
| 売上債権売却損 |
100万円
(非課税) |
|
|
その場合には未収金で処理せずに、売上債権売却損として処理をするようにしましょう。
2社間取引や、即日対応が可能なファクタリング会社であれば契約時に即入金される可能性が考えられます。
ファクタリングによるオフバランス化
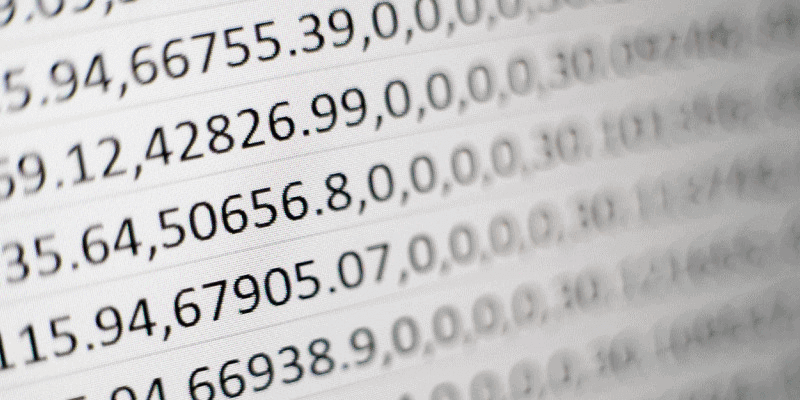
ファクタリングを利用することで、
賃借対照表(バランスシート)をオフバランス化させることができます。
オフバランス化することで、
総資産を増やさずに資金調達することができるのです。
なぜ、ファクタリングを利用することでオフバランス化が図れるのか詳しく解説していきます。
オフバランス化とは、賃借対照表(バランスシート)に計上される資産や負債をバランスシートからオフ(消す)すること。資産効率の改善が期待でき、収益性を高めることが可能。
オフバランス化できる理由
資金調達を行う上で、ファクタリングを利用すればオフバランス化することができます。
ファクタリングは資産である売掛債権を、
資産の部にある現金にするため資産の増加を防ぐことが可能です。
一方で銀行融資等で借入を行う場合、現金が資産の部に計上されるため総資産を増加させることになります。
銀行融資とファクタリングの総資産の増加について、例を用いて比較していきましょう。
【銀行融資の場合】
- <条件>
- 預金500万円
- 売掛金1,000万円
- →総資産1,500万円
| 借方科目 |
金額 |
貸方科目 |
金額 |
| 預金 |
500万円 |
短期借入 |
500万円 |
上記のように、銀行から借入を行うと流動資産が500万円増えています。
【ファクタリングの場合】
- <条件>
- 売掛金1,000万円
- →総資産1,000万円
| 借方科目 |
金額 |
貸方科目 |
金額 |
| 未収金 |
1000万円 |
売掛金 |
1000万円 |
ファクタリングの場合、資産である売掛金を現金に交換するため総資産が増加することがないのです。
上記のように、ファクタリングを利用するとオフバランス化することができます。
オフバランス化によって得られるメリットについて、次の章で詳しく紹介していきましょう。
決算時の区分表示と勘定科目
ファクタリングを利用した場合、
決算時はどのように会計処理を行えば良いの?
決算時の処理方法についても区分表示と勘定科目について紹介しておきましょう。
勘定科目は決算時も
「売上債権売却損」で大丈夫です。
表示区分については、
営業外費用と区分表示する必要があります。
詳しく紹介していきましょう。
決算時の区分表示は営業外費用
決算時のファクタリング手数料の区分表示は「
営業外費用」という扱いになります。
営業外費用とは、会社が本業以外で経常的に発生する費用のことです。
ファクタリングを利用して発生した手数料も、
財務的な活動から発生した費用なので営業外費用として区分されます。
ファクタリング2つのお金が非課税である理由
ファクタリングを利用して発生したお金は、消費税がかかるのか?
ファクタリングを利用すると、手数料・売掛債権売却額という2つのお金が発生しますよね。
これらは両方とも「
非課税取引」に該当するので、消費税の
課税対象外なのです。
なぜどちらも消費税がかからないの?と疑問に感じるでしょう。
その理由について詳しく紹介していきます。
ファクタリングは非課税取引だから
ファクタリングの手数料・売掛債権売却額が非課税である理由についてお伝えしていきましょう。
まず初めに消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引に対して課税対象としています。
しかし取引の中には、
非課税取引として該当するものがあるのです。
主な非課税取引
(2)有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
引用元:No.6201 非課税となる取引|国税庁
国税庁ホームページに記載されている非課税となる取引を参照すると、ファクタリングは上記の「
有価証券等の譲渡」に該当します。
金銭債権などの譲渡に該当する為、ファクタリングで発生したお金に消費税はかからないのです。
税金が減る?売上債権売却損は損金算入が可能
売掛債権売却損は、損金へ算入することが出来る?結論からお伝えすると出来ます。
しかし売掛債権売却損を損金へ算入することができるのは、
2つの条件に該当する場合のみ算入させることが可能です。
- ① 売掛債権を受け取ったファクタリング会社が、その債権に係る権利を実質的な制約なしに使用することができること
- ② 売却した売掛債権を支払期日前に買い戻す権利および義務を有してないこと
上記2つに該当する場合には、売掛債権売却損を損金へ算入することが出来ます。
損金に算入することで、
不要な税金を支払う必要がなくなり利益を少しでも減らない様にすることが可能です。
ファクタリングを利用した際には、上記2つの条件に該当するか確認してみましょう。
損金に算入できるのであれば、税金を減らすためにも損金へ算入することをオススメします。
まとめ
ファクタリングの勘定科目について紹介してきました。
ファクタリングの手数料は「
売上債権売却損」という勘定科目で処理します。
会計ソフトにより売上債権売却損という項目が無い場合には、
「雑損失」「債権割引料」などの勘定科目でも問題ないです。
またファクタリングで発生して手数料や、売掛債権売却額は消費税の課税対象とはなりません。
非課税取引の対象となるので、消費税の心配をする必要は無いのです。
会計処理にお困りの場合には、ぜひ参考にしてみてください。